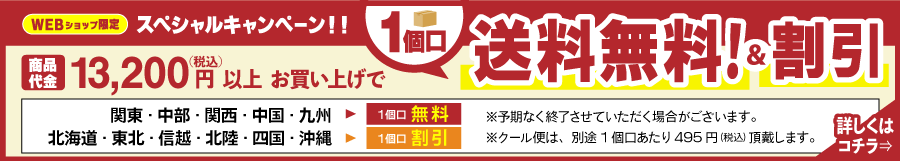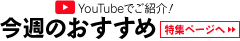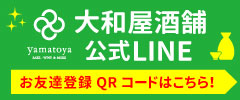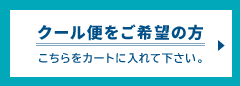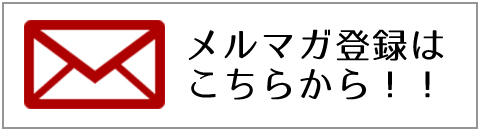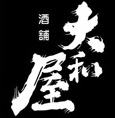※店舗と在庫を共有しているため、在庫のある商品でも欠品している場合がございます。
※同業者の方や転売目的のご購入と思われるご注文はお受けできません。
風の森の新しいシリーズ【S(エス)風の森】
2024年、「風の森」を醸す奈良県・油長酒造の新しい蔵が誕生しました。
美しい棚田のにある「葛城山麓醸造所」。
その「山麓蔵」で初めて搾ったお酒が「S風の森 Launch Edition」です。
蔵元団体J.S.P様運営のYouTubeもぜひご覧になってくださいませ。
尊い活動に涙してしまったスタッフでございます。
【蔵元コメント】
葛城山麓醸造所で造る、特別な風の森「S風の森」。
風の森の新たな挑戦、「S風の森」は「100年先に里山をつなぐ」という目標に向けて、始動いたしました。
標高が高く、豊富に湧き出る清涼な山水を使って秋津穂が栽培される、この地だからこそ造る事ができる、特別な風の森。
農業と共生し、この地で採れる秋津穂を使い酒を醸すことで葛城山麓の地の魅力やエネルギーを余す事なく表現していきます。
※お一人様1本までとさせていただきます。
【S(エス)風の森】
■「S」に込める想いとは、
・SATOYAMA/里山
・SCENE/景色、情景
・SANROKU/山麓
山麓蔵は葛城山麓地区の棚田の真ん中に位置します。
「風の森」の名前の由来となった、風の森峠を見渡す棚田の真ん中で、この里山の風景・景色を100年先に繋いで行きたい。
この地に醸造家が身を置き、この地で収穫された秋津穂を使う事で、葛城山麓地区の魅力を余す事なく映し出した酒を造ります。
■3つの約束
①葛城山麓産の秋津穂を使用
-天然の湧き水から作られる酒米「秋津穂」
-環境負担の少ないお米作り
-農薬化学肥料の不使用による環境負担の少ない栽培
②精米歩合 90%前後
-葛城山麓の風土をS風の森に転写する意味を込めて
できるだけお米を削らない
③奈良酒の伝統技法の応用
-古典技本菩提元研究会、古典技法によるお酒造り
そやしみず、高温発酵、菩提元など奈良酒の技法を使用
大地のエネルギーを使って、現代でしかできないお酒造りを融合させて造っていきます。
【テイスティングコメント】
洋ナシや青いバナナの香りに、吉野杉をふんだんに使用した新蔵だからこそ、杉の香りもほどよくレイヤーとして感じられます。
口に含むと非常に瑞々しくシャープな口当たりながら、葛城山麓地区の大地のエネルギーによる複雑味・秋津穂らしい苦みが後口を引き締めます。
ひと口含むと葛城山麓地区の棚田を吹き抜ける風の爽やかさや、太陽が降り注ぐ大地の力強さを感じることができる味わいです。
☆ぜひ特集されたYoutube動画もご覧ください!
【2024年11月28日に放送されました蔵元団体J.S.P運営YouTube】
- タイプ
- -
- 原材料
- 米(国産)、米麹(国産米)
- 原料米
- 2023年産 奈良県御所市葛城山麓産秋津穂
- 精米歩合
- 非公開(85%精米以上)
- アルコール分
- 15度
- 日本酒度
- -
- 酵母
- -
- 酸度
- -
- アミノ酸度
- -
【蔵元紹介】
油長酒造株式会社
奈良県御所市中本町
創業1719年。それまで営んできた製油業から酒造業へ転じる際、酒の命とも言える良質の水を求め、現在の地に蔵を築きました。
地下100mの深井戸から汲み上げる水は、葛城山や金剛山に降った雪や雨が長い時間をかけて地層にしみ込み、地層をくぐり抜ける間に、鉄やマンガン、有機物など酒造りに大敵の成分が取り除かれます。
代表銘柄は「風の森」、「鷹長」。
「風の森」
1998年に発売開始。生産量は現在約200石。2001年から、純米酒・純米吟醸・純米大吟醸の純米系のみの仕込みになりました。
地の水と、地の米と、地の風土にこだわった、オンリーワンの酒造り。
原料米には山田錦、雄町、露葉風、キヌヒカリ、アキツホを使用し、地元産のアキツホに最も重点を置いています。
笊籠採り(イカキどり)...
無濾過生原酒に頑ななまでにこだわり、常温でも生ヒネしない酒質にするために、12代目蔵元・山本氏が考案した独自の搾り方。モロミの中に、笊籬状(いかきじょう)のスクリーンを沈めて、モロミと清酒を分離する画期的な技法で、搾る際に酒が空気に晒されるのを防ぎます。
これは、長時間空気に晒される吊るし取りを凌ぐと考え、蔵元は所蔵していた全ての斗瓶を廃棄しました。