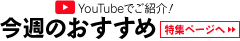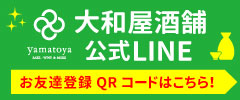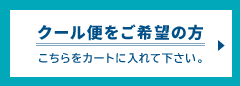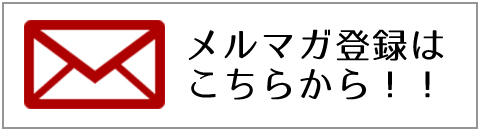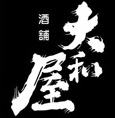※店舗と在庫を共有しているため、在庫のある商品でも欠品している場合がございます。
※同業者の方や転売目的のご購入と思われるご注文はお受けできません。
長らく欠番だったALPHA6、ついにリリース!
【蔵元コメント】
風の森は初期の頃、多種多様な酵母でお酒造りを行いましたが、目指す酒質と風の森の仕込水との相性を考え、最適な酵母は7号酵母という結論に至り、以来20年近く、7号酵母のみで醸してまいりました。
7号酵母は、1946年、大蔵省醸造試験場の山田正一氏が、長野県の銘酒真澄を醸す酒蔵から発見、「近代日本酒の礎」と称されました。
私自身も7号酵母の素晴らしさに魅了され続けています。
しかし、酒造りを続けてきた中で違う種の酵母への興味が募らなかったといえばそれは嘘になります。
私たちのフラッグシップ米秋津穂を違う酵母で醸せばどうなるのか、興味は尽きません。
【6号酵母】
7号酵母発見の16年前、6号酵母は1930年国税庁技術者・小穴富司雄氏の手により、秋田の銘酒新政を醸す酒蔵から発見されました。
それ以降に発見された協会酵母の親であり、全て遺伝的に6号の突然変異であることが判明しています。
低温発酵力の強い6号酵母は風の森との相性も良いのではないかとずっと思いを募らせていました。
今回、10年来親交を深めさせて頂いた新政酒造の佐藤祐輔さんから、6号酵母を分けていただき、風の森として20年ぶりに6号酵母を使用し、「風の森ALPHA6 6号への敬意」をリリースいたします。
2022までは精米歩合を6号にかけて、66%とさせていただきましたが、今回はもう少しお酒に複雑味を載せていきたいという私たちの考えから、精米歩合を70%に変更。
これによって少し複雑味や味わいの奥行きを表現してみました。
油長酒造の仕込み水の硬水の質感と相まって、今回の「風の森 ALPHA6 6号への敬意 2023」は今までのALPHA6の中では最も豊かで、奥行きのある質感を感じていただけることと思います。
※お一人様に付き2本までのご注文とさせて頂きます。
- タイプ
- -
- 原材料
- 米、米麹
- 原料米
- <奈良県産>秋津穂100%
- 精米歩合
- 70%
- アルコール分
- 14度
- 日本酒度
- -
- 酵母
- 6号酵母
- 酸度
- -
- アミノ酸度
- -
【蔵元紹介】
油長酒造株式会社
奈良県御所市中本町
創業1719年。それまで営んできた製油業から酒造業へ転じる際、酒の命とも言える良質の水を求め、現在の地に蔵を築きました。
地下100mの深井戸から汲み上げる水は、葛城山や金剛山に降った雪や雨が長い時間をかけて地層にしみ込み、地層をくぐり抜ける間に、鉄やマンガン、有機物など酒造りに大敵の成分が取り除かれます。
代表銘柄は「風の森」、「鷹長」。
「風の森」
1998年に発売開始。生産量は現在約200石。2001年から、純米酒・純米吟醸・純米大吟醸の純米系のみの仕込みになりました。
地の水と、地の米と、地の風土にこだわった、オンリーワンの酒造り。
原料米には山田錦、雄町、露葉風、キヌヒカリ、アキツホを使用し、地元産のアキツホに最も重点を置いています。
笊籠採り(イカキどり)...
無濾過生原酒に頑ななまでにこだわり、常温でも生ヒネしない酒質にするために、12代目蔵元・山本氏が考案した独自の搾り方。モロミの中に、笊籬状(いかきじょう)のスクリーンを沈めて、モロミと清酒を分離する画期的な技法で、搾る際に酒が空気に晒されるのを防ぎます。
これは、長時間空気に晒される吊るし取りを凌ぐと考え、蔵元は所蔵していた全ての斗瓶を廃棄しました。